ブログ
2025.10.14
令和7年度(2025年)の年末調整、税制改正で何が変わる?実務内容とスケジュール
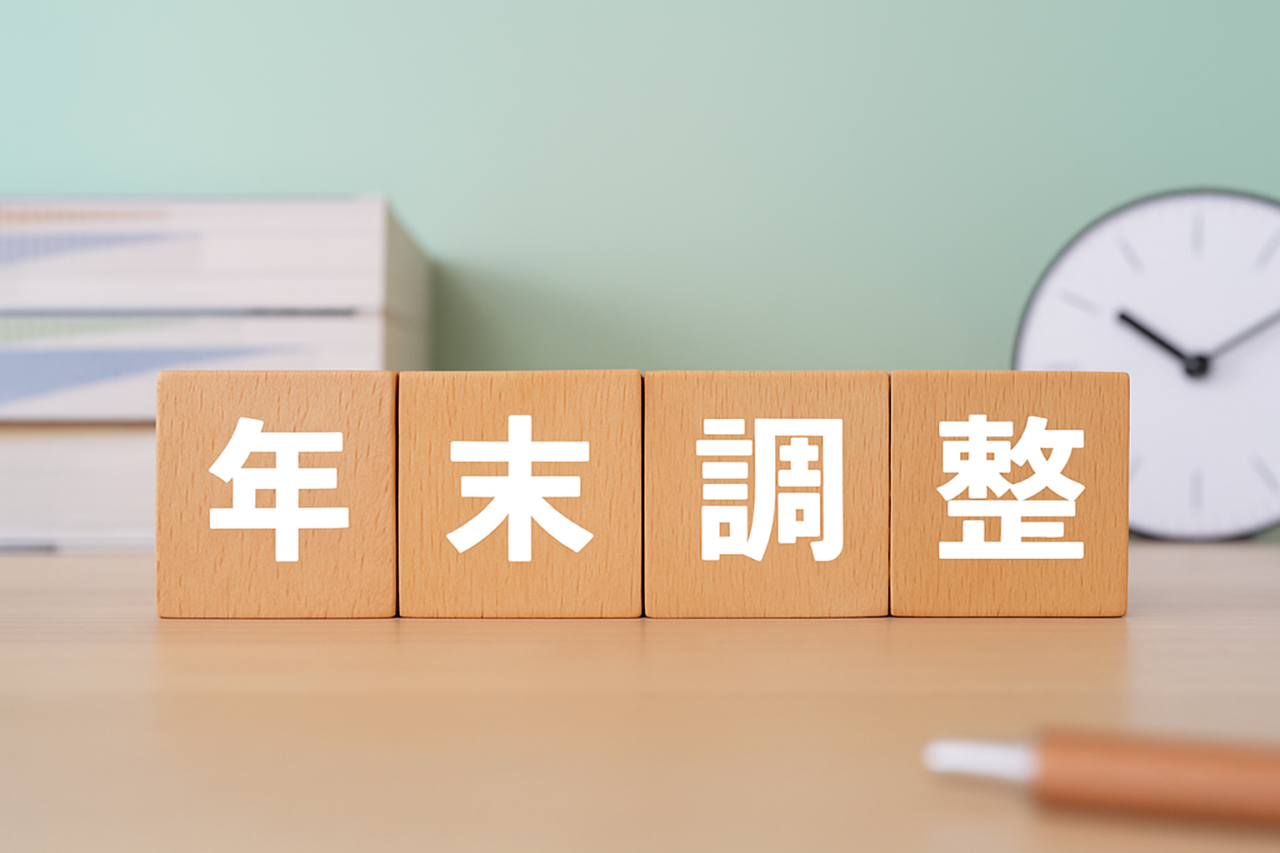
令和7年度(2025年)税制改正により、同年12月1日から所得税に関する重要な改正が施行されます。この改正は、長引く物価上昇や人手不足といった社会経済情勢の変化に対応し、納税者の負担軽減と労働供給の促進が目的です。
この改正により、企業の年末調整実務においても大幅な変更を伴います。特に、新たに創設された「基礎控除の特例」および「特定親族特別控除」は、控除額の判定基準が所得に応じて細分化されており、適用関係も複雑です。
そのため、人事・経理ご担当者様には、早期の段階からの正確な法改正理解と、計画的な準備が強く求められます。
この記事では、税制改正内容を踏まえ、企業の年末調整実務の具体的な対応方法・実務上の留意点を解説します。
令和7年度税制改正の概要
今回の税制改正では、個人の基礎控除および給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が行われます。
基礎控除および給与所得控除の引き上げ
基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下の納税者を対象に、一律58万円へ引き上げられます。さらに、給与収入金額に応じた「基礎控除の特例」による上乗せ措置が講じられます。
給与所得控除については、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
これらの見直しにより、いわゆる「103万円の壁」は最大「160万円の壁」へと変更され、就業調整の緩和が期待されます。
「特定親族特別控除」の創設
19歳以上23歳未満の特定扶養親族(主に大学生等)を有する世帯の税負担軽減を目的として創設されました。扶養親族の合計所得金額が一定額を超える場合でも、控除を段階的に適用できる制度です。
改正内容の詳細につきましては、以下の記事をご参照ください。

AOIみらい公式ブログ:
「年収の壁、所得税は160万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応」
年末調整における実務対応と準備事項
改正内容は、原則として2025(令和7)年分の所得税から適用され、同年12月以降の年末調整から具体的な対応が必要となります。企業のご担当者様が留意すべき実務上のポイントは、主に以下の4点です。
1. 各種申告書の変更点と確認項目
年末調整時に従業員から受理する各種申告書について、以下の変更点を正確に理解し、運用する必要があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・扶養親族等の合計所得金額要件が、現行の48万円以下から58万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下から123万円以下)へ引き上げられます。これにより、従来はパート収入が105万円であったため控除対象外だった配偶者などが、新たに控除対象となる可能性があります。
・全従業員に扶養状況を一度確認し、変更がある場合は申告書の修正・再提出が必要である旨を周知しましょう。
給与所得者の特定親族特別控除申告書(新設)
・「特定親族特別控除」の適用を受けるために、従業員からの提出が必須となる新しい申告書です。「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等と統合された兼用様式として、国税庁ホームページに公開されています。その年の最後に給与の支払を受ける日の前日までの提出が必要となるため、計画的な配布と記載要領の説明が重要です。
国税庁ホームページ 「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書
・基礎控除申告書:
納税者本人の「合計所得金額」に基づき「基礎控除の特例」が適用されます。特に副業等、給与所得以外の所得がある従業員の場合、合計所得金額の正確な見積もりが困難なケースも想定されます。国税庁から示される具体的な計算方法やQ&Aを注視し、従業員からの質問に的確に回答できる体制を整えましょう。
・配偶者控除等申告書:
配偶者の合計所得金額を算出する際、改正後の給与所得控除額(最低65万円)を適用して計算する必要がある点を、従業員に周知しましょう。計算の複雑化に伴い、申告書受理時のチェック体制を強化しておきましょう。
・所得基準の正確な判定:
「基礎控除の特例」の判定基準は、あくまで「合計所得金額」です。目安として示される「給与収入〇〇万円相当」という表現と混同しないよう、従業員に注意喚起するとともに、担当者も厳密な確認が求められます。
・限定措置の管理:
合計所得金額が132万円超655万円以下の層への特例加算は、令和7年・8年分の2年間限定措置です。令和9年分以降は適用がなくなるため、将来的な手取り額に影響が出ることを事前に従業員へ説明することが望ましいでしょう。
・適用範囲の誤認防止:
「特定親族特別控除」は、対象親族の合計所得金額が「58万円超123万円以下」という特定の範囲に限定されます。58万円以下であれば従来の扶養控除、123万円を超えればいずれの控除も適用外となるため、この区分を明確に説明する必要があります。
・重複控除の排除:
同一の親族について、夫婦それぞれが扶養控除や特定親族特別控除を重複して申告していないか確認が必要です。
複雑化する令和7年分の年末調整を円滑に進めていただくために、申告書受理時や計算時に注意すべき点をまとめたチェックリストをご用意いたしました。貴社の実務における確認漏れや計算ミスの防止、担当者様の業務負担軽減の一助として、ぜひお役立てください。
| 申告の種類 | チェック項目 | 備考 |
| ご自身の基礎控除 | 自身の今年1年間の給与収入、および給与以外の所得(副業など)を含めた「合計所得金額の見積額」を計算したか | |
| ご自身の基礎控除 | 上記の「合計所得金額の見積額」に基づき、ご自身の「基礎控除額」がいくらになるかを確認したか | |
| ご自身の基礎控除 | 配偶者の今年1年間の「合計所得金額の見積額」を確認したか | |
| 配偶者控除 | 配偶者の収入がパート・アルバイト等の給与のみの場合、新しい給与所得控除(最低65万円)で計算されていることを確認したか | |
| 扶養控除 | 扶養している親族について、新しい所得要件(合計所得金額58万円以下、給与収入のみなら123万円以下)で、扶養に該当するかを確認したか | これまでが扶養に含めていなかった親族が、今回の改正で対象になる可能性があります |
| 特定親族特別控除 | 年齢が19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)の扶養親族がいるか | |
| 特定親族特別控除 | 特定親族特別控除の対象親族がいる場合、その親族の「合計所得金額の見積額」を確認したか | |
| 特定親族特別控除 | 特定親族特別控除の対象親族がいる場合、所得額に応じて「扶養控除」「特定親族特別控除」のどちらに該当するかを正しく判断したか | 扶養控除:合計所得58万円以下 特定親族特別控除:合計所得58万円超〜123万円以下 |
| 扶養控除 | 扶養親族(特に特定親族特別控除の対象者)について、ご自身の配偶者など、他の親族が扶養として申告していないか | 同一の親族は、一人しか扶養に取れません |
| その他 | 生命保険料や地震保険料などの控除証明書はすべて揃っているか |
| カテゴリ | チェック項目 | 備考 |
| 提出書類の基本情報 | 必要な申告書がすべて提出されているか(扶養控除等申告書、基礎控除申告書(兼用様式)など) | |
| 提出書類の基本情報 | 従業員本人の氏名・住所・マイナンバーが正しく記載されているか | すでにマイナンバーを把握済の場合はマイナンバー記載不要 |
| 提出書類の基本情報 | 保険料控除証明書など、必要な添付書類が揃っているか | |
| 基礎控除 | 従業員本人の「合計所得金額の見積額」が記載されているか | |
| 基礎控除 | 記載された「基礎控除額」が、合計所得金額の区分に応じて正しく選択されているか | 95万円、88万円、68万円、63万円、58万円、またはそれ以下の逓減額 |
| 基礎控除 | 合計所得金額2,500万円超の場合、控除額が0円となっているか | |
| 配偶者控除等 | 配偶者の氏名・マイナンバー・合計所得金額の見積額が記載されているか | |
| 配偶者控除等 | 配偶者の所得が給与所得の場合、改正後の給与所得控除(最低65万円)を適用して合計所得金額が算出されているか | |
| 配偶者控除等 | 算出された控除額が、従業員本人と配偶者の所得金額の組み合わせに対して正しいか | |
|
扶養控除 |
各扶養親族の合計所得金額の見積額が記載されているか | |
| 扶養控除 | 各扶養親族の合計所得金額が、改正後の所得要件(58万円以下)を満たしているか | |
| 扶養控除 | 年齢等に応じた控除区分(一般、特定、老人など)が正しいか | |
| 特定親族特別控除 | 対象親族の年齢が19歳以上23歳未満であるか | |
| 特定親族特別控除 | 対象親族の合計所得金額が「58万円超~123万円以下」の範囲内であるか | |
| 特定親族特別控除 | 記載された「特定親族特別控除額」が、対象親族の所得金額の区分に応じて正しく選択されているか | 63万円~3万円の段階的な控除額 |
| 特定親族特別控除 | 申告書に、他の親族が同一人物を扶養としていないか(重複控除の有無)を確認する | |
| 最終確認 | 年末調整システムを利用する際、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が正しく反映されているか | |
| 最終確認 | 特定親族特別控除の適用がある場合、源泉徴収簿や源泉徴収票の様式・記載方法が改正後のものに対応しているか | |
| 最終確認 | 基礎控除の特例について、令和7・8年分限定の措置であることをシステム上または手計算で反映できているか |
2. 年末調整・給与計算システムの準備
控除額計算方法が大幅に変更されるため、使用しているシステムの適切なアップデートが不可欠です。
・システム改修内容の確認:
利用中のシステムが、改正後の基礎控除(特例加算、時限措置含む)、給与所得控除、特定親族特別控除の計算方法、各種所得要件の変更、新しい兼用様式などに正確に対応可能か確認します。
・アップデートの適用と検証:
アップデートの提供時期を確認し、社内適用スケジュールを策定します。適用後は、テストデータを用いて計算結果を検証し、本番業務開始前に問題点を解消しておきましょう。
・関連帳票・テーブルの更新:
計算時に参照する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されました。国税庁公式サイトに公開されていますので、ご確認ください。
また、特定親族特別控除の適用がある場合、既存の源泉徴収簿では対応できない可能性があるため、システム上の管理方法や手計算の場合の記載方法を事前に確認しておきましょう。
3. 従業員への周知および情報提供
制度改正を円滑に導入するためには、従業員への事前の丁寧な情報提供が不可欠です。
・説明会の開催・相談窓口の設置:
全従業員または対象者層に向けた説明会を実施することが有効です。また、個別の具体的な質問に対応可能な相談窓口を人事・経理部門に設置し、従業員の疑問点を解消できる体制を整えます。
・住民税への影響に関する説明:
所得税の控除額が、そのまま住民税に同額で反映されるとは限りません。住民税の計算は翌年度になるため、所得税の減税効果と翌年の住民税額との間に認識のズレが生じないよう、「所得税と住民税では制度や計算時期が異なる」ことを事前に説明しておきましょう。
4. 社内スケジュールの策定
計画的な準備・実行のため、早期に社内スケジュールを策定しましょう。
【〜9月】情報収集・準備期間:
国税庁等から発出される最新情報を継続的に収集し、社内の対応方針を確定。システムベンダーと連携し、改修・テスト計画を策定・実施します。担当者向けの社内研修もこの時期に企画・実施し、知識の標準化を図ります。
【10月〜11月】周知・申告書回収期間:
従業員への説明会開催等により、改正内容と手続きの変更点を周知徹底します。新様式を含む各種申告書を配布し、回収を開始するとともに、提出されたものから順次内容のチェックを進め、不備があれば速やかに修正を依頼します。
【12月】計算・精算期間:
回収・チェック済みの申告書に基づき、改正後の控除額を適用して年末調整計算を実施します。特に新設された控除の計算結果については、複数人による検算・検証作業を徹底しましょう。
【翌年1月〜】法定調書提出・総括期間:
税務署および市区町村へ法定調書等を提出します。当年の年末調整実務を総括し、次年度の改善に繋げましょう。
まとめ
令和7年度税制改正は、多くの給与所得者にとって税負担軽減に繋がる一方、年末調整の実務は大幅に複雑化します。
企業のご担当者様におかれましては、本記事で示した実務上の留意点を参考に、早期の段階から情報収集に着手し、システム対応や従業員への周知計画を策定することが、年末調整業務を円滑に遂行するための鍵となります。
税理士法人AOIみらいは、グループ会社に社会保険労務士法人を持ち、いわゆる「年収の壁」の変更に伴う社会保険に関するご相談や、就業規則の見直しなどおもワンストップでご支援いたします。
改正に伴う年末調整の実務対応に少しでも疑問やご不安がございましたら、税理士法人AOIみらい(東京都新宿区)まで、どうぞお気軽にご相談ください。




