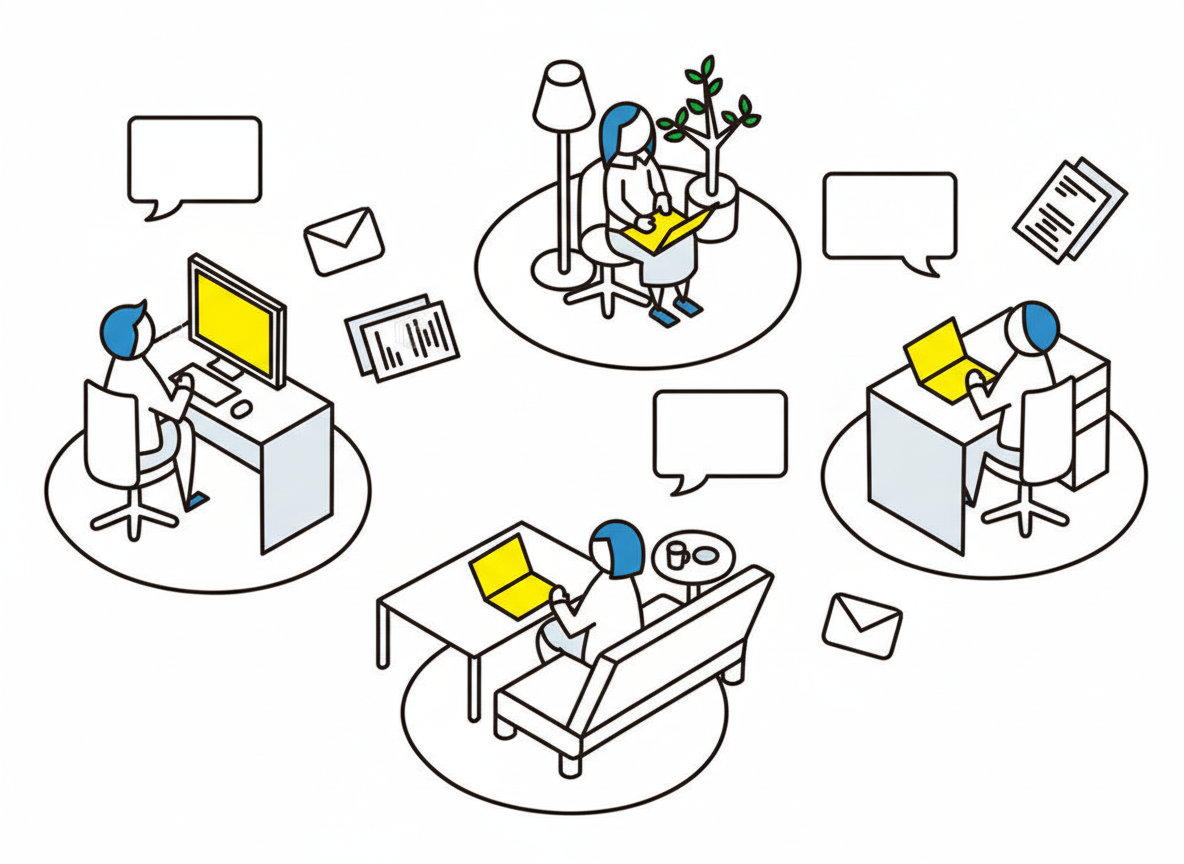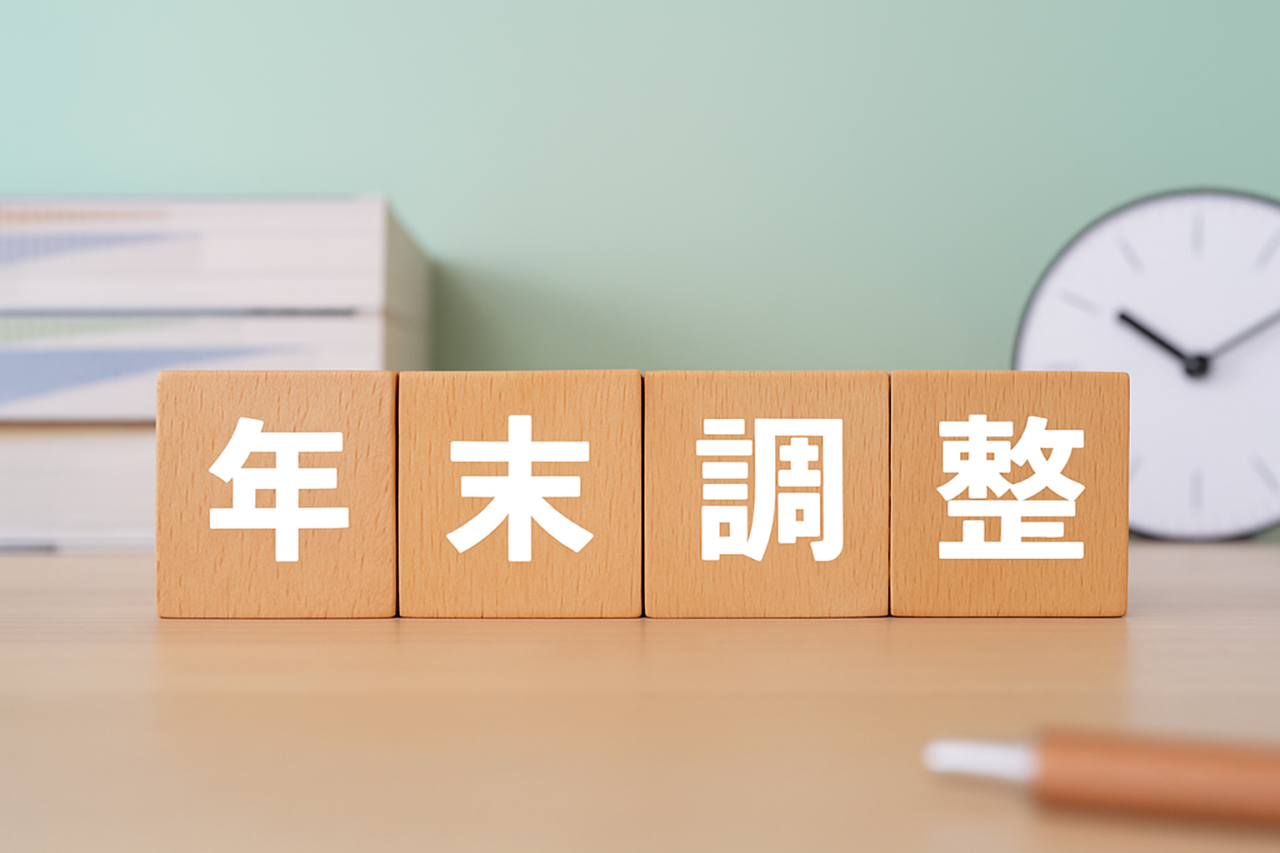ブログ
2025.11.25
2026年度(令和8年度)の税制改正はどうなる?各省庁の主要な要望まとめ

2026年度(令和8年度)の税制改正について、公表の時期が近づいてきました。各府省庁からは、8月に税制改正要望が税制調査会に提出されており、12月中旬に税制改正大綱としてまとめられます。
今回の税制改正要望は、資産運用の促進、持続可能な社会への転換などが中核となっています。
この記事では、資産形成・金融取引、相続・事業承継など、各府省庁の要望を紹介します。
※2025年12月19日に税制改正大綱が発表されました。詳細は速報記事をご覧ください。
【速報】2026年度(令和8年度)税制改正大綱を解説
資産形成・金融取引
こ金融庁や経済産業省は、日本を国際競争力のある金融市場へと変貌させるため、税制面からの大胆なテコ入れを要望しています。
暗号資産取引に対する分離課税化の検討開始
現在、暗号資産取引の利益は原則として雑所得として扱われ、最高約55%の総合課税が適用されますが、金融庁は、暗号資産取引の利益を株式等の売却益と同様に約20%の分離課税とするよう、税制改正要望を提出しています。
これが実現すれば、日本の暗号資産市場への機関投資家や大規模な個人投資家の参入障壁が下がります。
(金融庁)
NISA制度のさらなる簡素化と拡充
2024年に拡充されたNISA(少額投資非課税制度)の定着と利便性向上も主要な要望項目です。
金融庁は、NISA口座開設後10年経過時などに金融機関が顧客に対して義務付けられている所在地確認手続きについて、その事務負担に配慮した簡素化を求めています。手続きの簡素化により、金融機関のコストを軽減し、より多くの方がNISAを利用しやすい環境を整えることを目的としています。
(金融庁)
金融所得課税の「一体化」推進
金融商品に係る損益通算範囲の拡大、すなわち金融所得課税の一体化についても、農林水産省と経済産業省が共同で要望しています。異なる種類の金融商品間で損失と利益を柔軟に相殺できるようになれば、投資家はリスクヘッジを行いやすくなり、より多様な資産運用戦略を採用できるようになります。
(金融庁、農林水産省、経済産業省)
企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長
企業年金(確定拠出年金、確定給付企業年金等)の積立金には、本来1%の特別法人税が課されていますが、年金資産の運用に著しい影響を及ぼすため、平成11年度から現在に至るまで課税が凍結されています。
(金融庁、厚生労働省)
外国組合員に対する課税の特例の見直し
海外投資家(外国組合員)が日本の投資ファンド(投資組合)へLP(有限責任組合員)として出資し、国内源泉所得を得た場合に、その所得に対する課税を非課税とする特例措置に関するものです。
現在、米国、英国、シンガポールといった主要国ではこの種の所得は通常非課税であり、日本が海外とのイコールフッティングを図り、グローバルなネットワークを持つ海外投資家を呼び込む環境強化が見直しの目的です。見直し内容は、この特例措置の適用要件や手続きの簡素化が焦点となります。
(金融庁、経済産業省、総務省)
企業支援
経済産業省を中心に、企業の脱炭素化投資や生産性向上のための優遇措置、および中小企業の事業継続性を支える税制の拡充が求められています。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長等
本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間の取得価額の合計額300万円を限度に、その取得価額全額を損金に算入できる制度です。本税制措置により、パソコンや情報処理ソフトウェアといった少額資産の取得を促し、事務処理能力の向上と事業効率の向上を図ります。
(総務省)
長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長
事業の用に供している土地建物等(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に新しい事業用資産(買換資産)を取得した場合に、課税を将来に繰り延べることができる優遇措置です。特に、譲渡資産と買換資産の所在地に応じて課税繰り延べの割合が細かく定められており、事業構造や地域の活性化を促すための資産の入れ替えを後押しします。
この特例の適用期限を延長し、企業の柔軟な事業展開と資産の効率的な活用を支援することが要望されています。
(経済産業省)
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)の延長等
カーボンニュートラルの実現に向け、企業による脱炭素投資を加速するための税制措置の延長が要望されています。
この制度は、生産工程の効率化等により炭素生産性を向上させる設備を取得した場合、企業の規模や炭素生産性の向上率に応じて、50%の特別償却、または最大14%(中小企業者等)の税額控除を措置するものです。
要望の焦点は、単なる投資の量ではなく、付加価値向上と脱炭素化を両立させる質の高い戦略的投資を促進し、産業競争力の強化を図ることにあります 。現行の適用期限は2026年3月31日までです。
(経済産業省)
相続・事業承継
円滑な事業承継や、相続税非課税限度額の見直しなど、世代間の資産移転を円滑化し、遺族の生活基盤を確保するための措置が要望されています。
死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
死亡保険金の非課税限度額は、現在「法定相続人1人当たり500万円」と定められています。金融庁は、物価上昇や社会情勢の変化を考慮し、この非課税限度額を引き上げることを要望しています。
(金融庁)
上場株式等の相続税に係る見直し
上場株式等の相続税評価や納税に関する手続き、課税のあり方について見直しを行う要望です。金融所得課税全体の見直しや資産運用立国の推進と関連し、円滑な世代間の資産移転を促すための制度的な調整を目的としています。
(金融庁)
事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等
経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、特例承継計画の期限延長など、制度の拡充を要望されています。
これにより、後継者への円滑な事業の引き継ぎを後押しし、中小企業の生産性維持・向上を支援します。
(厚生労働省、経済産業省)
相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置の延長
相続税等の納税が猶予されている農地について、その農地が道路や学校などの公共事業用地として国や自治体に譲渡される場合、納税猶予が打ち切られ、過去に遡って利子税が課される可能性があります。
公共事業への用地提供を円滑化するため、この場合に生じる利子税の納付を免除する特例措置があり、公共性の高い事業に協力する納税者に対し、不利益が生じないよう配慮するための措置として延長が要望されています。
(農林水産省、国土交通省)
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
この特例は、持分あり医療法人が地域住民に対して良質かつ適切な医療を継続的・安定的に提供できるよう、持分なし医療法人への移行を促進するために、移行時の相続税・贈与税の納税猶予等を措置するものです。
厚生労働省は、移行を促進するため、特例措置の延長や移行期限の緩和を要望しています。
(厚生労働省)
住宅・リフォーム関連
住宅市場の需要が既存住宅の改修へとシフトする中で、経済産業省・国土交通省は以下の特例措置の延長・拡充を要望しています。これらの措置は、既存住宅の性能向上を図るリフォーム投資へのインセンティブとして機能し、住環境の質の改善を促します。
また、単なる延長だけでなく工事費用相当額等の見直しも要望されています。現行制度の利用実態や物価動向、工事実績を踏まえて、税制優遇がより実態に即したものとなるよう制度の適正化を図る意図があります。
- 既存住宅の省エネ改修等に係る軽減措置の延長
- 既存住宅の省エネ改修等に係る標準的な工事費用相当額等の見直し
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する標準的な工事費用相当額等の工事実績を踏まえた見直し
- 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置
- 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て対応リフォームに係る特例措置
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長
(国土交通省、復興庁、こども家庭庁、環境省、金融庁、財務省)
その他
国土強靱化の財源確保や、全世代型社会保障、取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)の適正化など、国家戦略と社会インフラに関わる重要な財政・税制上の論点が集まっています。
第1次国土強靱化実施中期計画等を踏まえた財源確保方策の検討の開始
大規模なインフラ投資や老朽化対策、および大規模災害への備えといった国土強靱化に必要な安定財源を確立するため、財務省が議論の開始を要望しています。
これは、将来的な増税、既存の租税特別措置(租特)の廃止・縮小、または税体系自体の抜本的な見直しに繋がる可能性があり、今後の税制改正における最大かつ最も重要な財源論の論点となります。
(財務省)
全世代型社会保障構築のための税制上の所要の措置
少子化対策や高齢者医療・介護など全世代型社会保障制度の構築に向け、広範な税制措置要望が提出されています。
地方自治体が独自に行う子育て支援サービス(例:ベビーシッター利用料補助)の給付が所得税の雑所得として課税される事例に対し、非課税化の検討を求めるほか、産後ケア事業に要する費用に対する消費税非課税措置の創設などが含まれます。
(厚生労働省、総務省)
生命保険料控除制度の拡充の恒久化等
個人の自助努力による安定的な生活設計を支援するため、現行の生命保険料控除制度(一般、介護医療、個人年金)について、その拡充措置の恒久化が要望されています。
これにより、控除限度額の引き上げや控除対象の安定化が図られ、長期的かつ計画的な個人の資産形成や保障を後押しします。
(金融庁、厚生労働省、総務省)
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の制度改善に伴う所要の措置
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)は、企業が認定された地域再生計画に位置付けられた事業に寄附を行った場合に、最大で寄附額の約9割の税が軽減される制度です。
本要望は、地方への資金の流れを促進する一方で、制度の適正化を目的としています。具体的には、寄附金が事業費を上回らないように管理することや、寄附企業に対し寄附の見返りとして経済的利益の供与を行わないよう徹底するための改善措置が中心となります。
(内閣府、総務省)
社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和
社会医療法人等が開設する医療機関が、公的保険の適用外となる訪日外国人患者の自由診療を受け入れた場合、診療費の請求金額に要件が設けられています。本要望は、訪日外国人診療に伴う医療機関の負担に鑑み、訪日外国人に対して請求できる診療費の上限を緩和することを求めるものです。
これにより、医療機関が安心して外国人患者を受け入れられる環境を整備し、受入体制の充実を図ります。
(厚生労働省、農林水産省)
東日本大震災に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長
東日本大震災により被害を受けた中小企業者や被災者に対し、日本政策金融公庫等が特別貸付けを行う際に作成される消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする特例措置の適用期限の延長が要望されています。
(財務省、国土交通省、厚生労働省、経済産業省)
取引相場のない株式の評価通達(類似業種比準方式)の適正化
会計検査院は令和5年度決算検査報告において、非上場株式の評価における類似業種比準方式について、純資産価額方式と比較して評価額が「相当程度低く算定される傾向」にあることを指摘しました。
参考:会計検査院 令和5年度決算検査報告 「第4 相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」
特に、類似業種比準方式の適用割合が高い大規模な会社ほど、評価額が相対的に低くなるという構造的な問題が指摘され、異なる規模区分の納税者間で「評価の公平性が必ずしも確保されていない」という懸念が示されています。
国税庁に対しては、評価の適正化を図るため、以下の対応が強く求められています。
①継続企業としての実態の反映:
企業の収益性や資産性がより正確に反映されるよう、評価通達を見直すこと。
②恣意的な操作の排除:
非経常的な損失計上や資産の移転等が恣意的に行われ、株価が不当に低くなることを防止する規定を設けること。
③配当要素の重要性:
類似業種比準方式の計算において、株価決定に重要な配当金額を軽視すべきではない。
会計検査院の指摘の重さを鑑みると、今後の税制改正で見直しが行われる可能性があります。
まとめ
今回紹介した内容は、各府省庁から提出された要望の一部です。要望詳細は各府省庁の公式サイト等に掲載されていますので、そちらも併せてご確認ください。
2026年度(令和8年度)税制改正大綱は12月中旬に公表される予定です。正式な発表があり次第、税理士法人AOIみらいの公式ブログで紹介いたします。
今後のスケジュール
2025年11月〜12月頃:与党税制調査会による最終調整
2025年12月中旬:税制改正大綱の決定・発表
2026年1月~2月頃:改正法案の閣議決定・国会提出
2026年3月末頃:国会審議・法案成立
2026年4月1日以降:改正法の施行、適用開始